将来の相続に備え、大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぎたいと考える方は多いでしょう。その有効な手段として、相続時精算課税制度を活用して不動産を生前贈与する方法が注目されています。この制度は2024年の改正でさらに使いやすくなりました。この記事では、制度の基本から不動産贈与におけるメリット、そして後悔しないための注意点まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
相続時精算課税制度の基本と2024年改正のポイント

まずは、相続対策の重要な選択肢となる相続時精算課税制度の仕組みを正しく理解することから始めましょう。2024年からの改正点を押さえることで、より効果的な活用が見えてきます。この制度は、一度選択すると暦年贈与には戻れないため、基本的な知識をしっかりと身につけておくことが大切です。
2,500万円まで非課税になる特別控除とは
この制度の最も大きな特徴は、贈与者一人につき合計2,500万円という大きな非課税枠が設けられている点です。これは、親や祖父母から18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に利用できる特別控除額を指します。複数年にわたって贈与した場合でも、その合計額が2,500万円に達するまでは贈与税がかかりません。
暦年贈与との違いと制度選択の注意点
生前贈与には、毎年110万円まで非課税の「暦年贈与」もあります。相続時精算課税制度を選択すると、その特定の贈与者からの贈与については、暦年贈与の非課税枠は使えません。どちらの制度が有利かは、贈与する財産の額や種類、将来の相続設計によって大きく異なります。そのため、安易に選択するのではなく、長期的な視点で比較検討することが重要です。
新設された年110万円の基礎控除のメリット
2024年の税制改正により、従来の2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除分の贈与は、将来の相続財産に加算されることなく、贈与税の申告も原則不要です。これにより、毎年少額の贈与を非課税で行いながら、大きな財産の移転も計画できるなど、制度の柔軟性が格段に向上しました。
相続時精算課税による不動産贈与のメリット
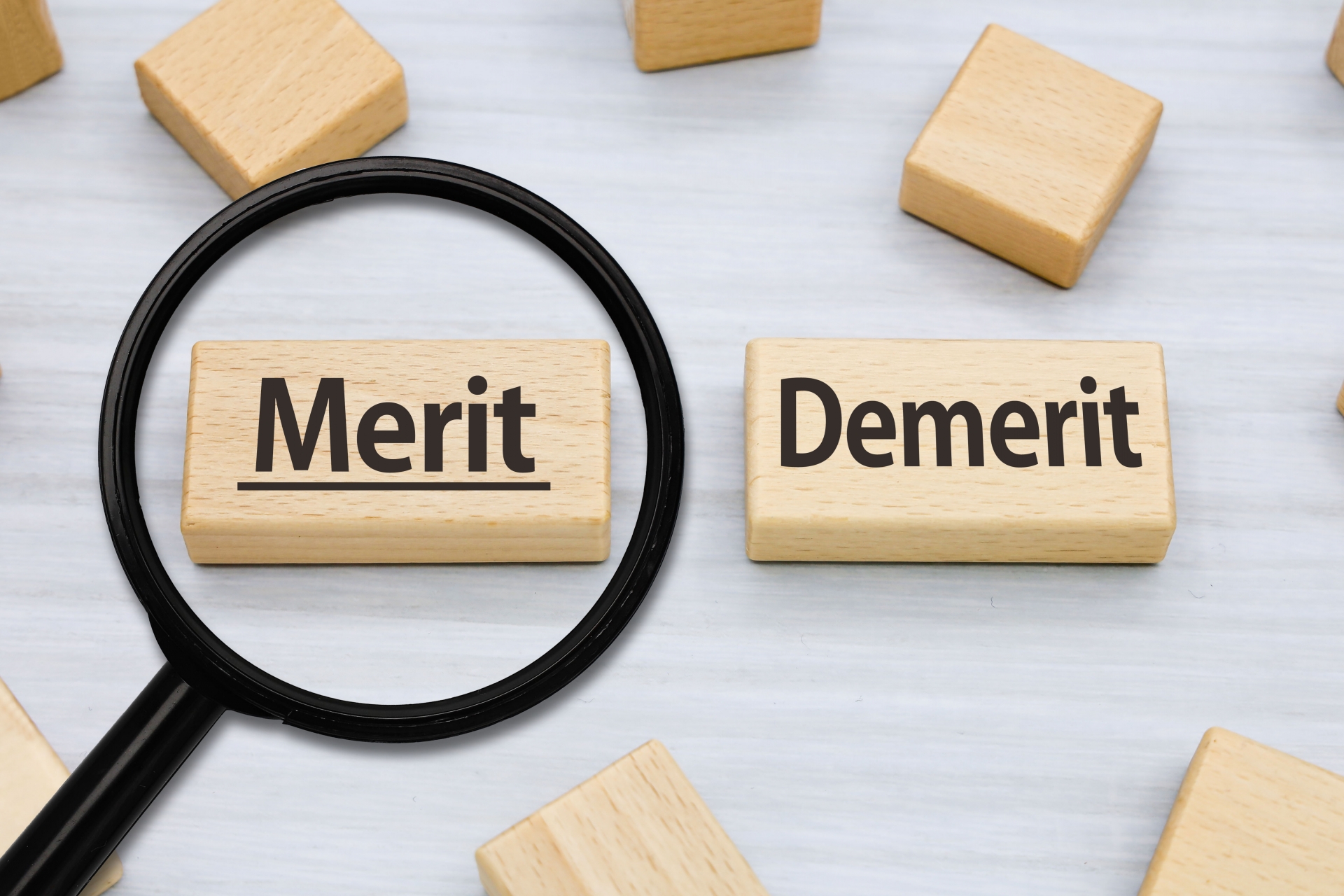
では、なぜ相続時精算課税制度は、特に不動産の生前贈与で活用するとメリットが大きいのでしょうか。それは、不動産という資産の特性と制度の仕組みがうまく噛み合うからです。将来の資産価値の変動や収益性まで考慮に入れることで、不動産を活用した相続時精算課税は、現金での贈与にはない大きな利点を生み出す可能性があります。
贈与時の評価額で固定される大きな利点
不動産をこの制度で贈与する最大のメリットは、相続税を計算する際の評価額が「贈与時の価格」で固定されることです。例えば、将来的に値上がりが期待される地域の土地や建物を早めに贈与しておけば、相続発生時にその価値がどれだけ上がっていても、贈与時の低い評価額で相続財産に加算されます。これにより、将来の相続税負担を効果的に抑えることが可能になります。
収益物件の贈与で所得の移転を図る方法
アパートや賃貸マンションといった収益物件の贈与も非常に有効な手段です。物件そのものを子や孫へ贈与することで、それ以降に発生する家賃収入も子や孫のものになります。これは、親世代の資産が増え続けるのを防ぐと同時に、子世代が納税資金や自身の資産を形成する手助けにもなります。
不動産評価額の計算方法と専門家の役割
贈与する不動産の評価額は、現金とは異なり専門的な計算が必要です。土地は国税庁が定める路線価、建物は市町村が管理する固定資産税評価額を基に算出するのが一般的です。これらの評価額は時価よりも低くなる傾向があるため、その差額分だけ節税効果が生まれます。ただし、評価は複雑なため、正確な価額を把握し、最適な贈与計画を立てるには税理士など専門家の助言が欠かせません。
制度利用で後悔しないための手続きと注意点

相続時精算課税制度はメリットが大きい反面、知っておくべき重要なルールや注意点も存在します。手続きを怠ったり、デメリットを理解しないまま進めたりすると、かえって損をしてしまうかもしれません。ここでは、制度を安心して活用するために、必ず押さえておきたい手続きの流れと、特に気をつけるべきポイントについて解説します。
贈与を受けた翌年の確定申告が必須
この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必ず税務署へ贈与税の申告書を提出しなくてはなりません。たとえ贈与額が非課税枠の範囲内で税額がゼロであっても、初回の申告は必須です。この手続きを忘れてしまうと、2,500万円の特別控除や110万円の基礎控除が認められず、多額の税金が発生する恐れがあります。
小規模宅地等の特例が使えなくなるデメリット
相続税の負担を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。これは、被相続人の自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる強力なものです。しかし、相続時精算課税制度を利用して贈与した不動産には、この小規模宅地等の特例を適用できません。
二次相続まで見据えた長期的な視点の重要性
相続対策を考える際は、目先の一次相続だけでなく、その次の二次相続まで含めた長期的な視点が不可欠です。今回の贈与が、家族全体の将来の税負担にどのような影響を与えるかを総合的に判断しなくてはなりません。ご家族の状況や資産構成をふまえ、最適な承継プランを家族で話し合い、専門家と共に練り上げていくことが成功のカギとなります。
まとめ
この記事で解説したように、相続時精算課税制度を使い不動産を活用することは、計画的な資産承継を実現する有力な選択肢です。特に2024年の改正で年間110万円の基礎控除が加わったことで、その利便性は大きく向上しました。しかし、一度選択すると後戻りできない点や、小規模宅地等の特例が使えなくなるなどの重要な注意点も存在します。ご自身の状況に本当に合致しているか、慎重な判断が求められます。



コメント