不動産経営において、節税は収益最大化の重要な課題です。規模拡大に伴い個人の税負担は増大しがちですが、そこで注目されるのが資産管理会社などの法人活用になります。この対策は所得税と法人税の税率差を利用するだけでなく、経費の範囲拡大や相続対策にもつながります。この記事では、不動産オーナーが知るべき法人活用の基本と、具体的な節税手法について解説します。
不動産経営の節税対策、法人活用の基礎知識
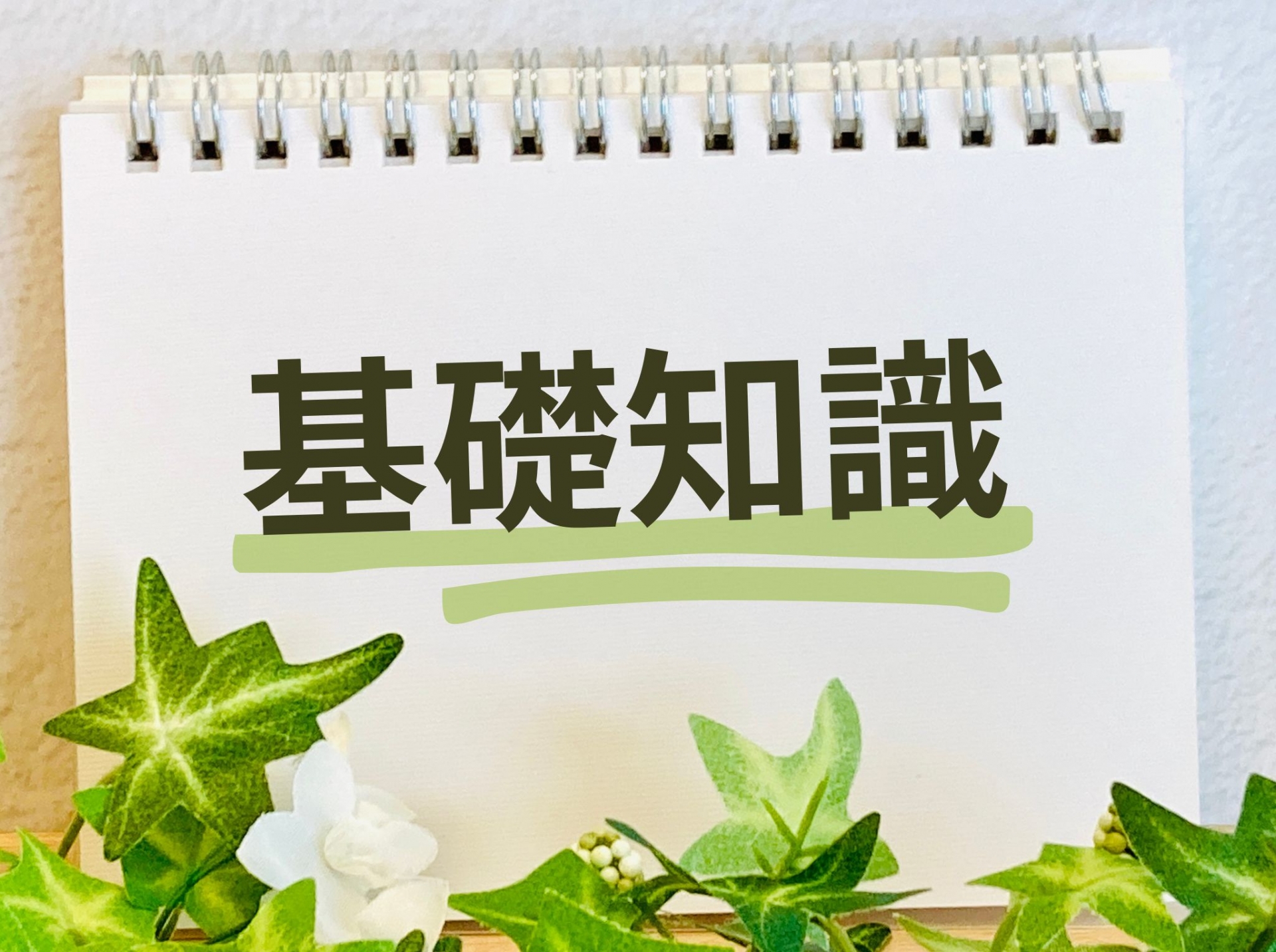
不動産オーナーが節税を考える際、法人活用は有力な選択肢になります。個人事業のままでは所得が増えるほど税率が高まりますが、法人化によって違う税制が適用されるためです。この対策の仕組みを正しく理解することが、効果的な節税への第一歩になります。
なぜ法人化が節税対策になるのか
法人化が不動産経営の節税対策になる理由は、個人に課される所得税と法人に課される法人税の税率構造の違いです。所得税は累進課税で、所得が高いほど税率も45%まで上昇します。一方、法人税は資本金や所得額で変わりますが、おおむね一定です。このため、不動産所得から減価償却費などを引いた課税所得が一定額を超えると、個人の税率が法人税率を上回ります。
個人経営と法人経営の税率の違い
個人経営の場合、不動産所得には所得税、住民税、事業税がかかります。所得税は課税所得に応じて5%から45%の7段階で変わる超過累進税率です。これに住民税約10%が加わります。対して法人経営では、法人税、法人住民税、法人事業税が課されます。法人税率は所得800万円を境に税率が変わるものの、個人の税率よりは低く設定されています。
法人化を検討すべきタイミング
法人化を考える一般的な目安は、課税所得が900万円を超えるタイミングです。この水準を超えると、所得税と住民税を合わせた税率が法人税の実効税率を上回る可能性が高くなります。ただし、これはあくまで目安であり、個々の状況によって最適解は違います。例えば、所有物件の規模や将来の事業展開、相続対策の必要性なども重要な判断材料です。
不動産節税対策としての法人活用のメリット

不動産の法人活用は、単に税率が低くなるだけではありません。経費として認められる範囲が広がり、所得分散も可能になるなど、さまざまな面から節税対策が実現します。さらに、個人の資産とは切り離されるため、円滑な事業承継や相続税対策にもつながる点が魅力です。
経費計上できる範囲の拡大
法人化により、個人事業では経費計上が難しかった支出も損金として算入できる場合があります。退職金は税制上優遇されており、節税効果が期待できます。また、家族を役員にすることで、その給与も経費として計上可能です。さらに、法人所有の社宅を役員に貸し付けることで家賃の一部を経費にできるなど、個人事業に比べて経費の自由度が高まることが法人活用のメリットです。
役員報酬による所得分散
法人から役員であるオーナー自身や家族へ役員報酬を支払うことで、不動産所得を給与所得として分散できます。給与所得には給与所得控除が適用されるため、課税対象額を圧縮する効果があります。家族を役員にして報酬を支払えば、世帯全体での所得分散が可能になり、さらなる節税対策につながるため、適切な報酬設定が重要です。
相続税対策としての有効性
法人活用は相続税対策としても機能します。個人で不動産を所有している場合、相続発生時にはその不動産の評価額が直接相続税の課税対象になります。一方、法人所有であれば、相続の対象は不動産そのものではなく、その法人の株式です。役員報酬や配当を通じて計画的に個人の財産を親族に移転したり、相続人へ株式を少しずつ贈与したりすることで、相続財産を圧縮できます。
不動産の法人活用で節税対策を進める際の注意点

法人活用による節税対策はメリットが大きい一方、設立や維持に伴うコスト、複雑な手続きなどの注意点も存在します。これらのデメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることが欠かせません。専門家の助言を得ながら、慎重に計画を進める必要があります。
設立・維持にかかるコスト
法人の設立には、定款認証や登記のための費用として数十万円が必要です。司法書士などの専門家に依頼すれば、その報酬も発生します。また、設立後も法人住民税の均等割が、赤字であっても毎年最低7万円程度かかります。税務申告も個人事業より複雑になるため、税理士への顧問料も考えるべきコストです。
法人名義への不動産移転手続き
個人所有の不動産を設立した法人へ移転する場合、さまざまな手続きと税金が発生します。具体的には、不動産取得税や登録免許税がかかります。また、個人から法人への売却という形をとるため、適正な時価で取引しないと、個人側に譲渡所得税が課されたり、法人側に受贈益が認定されたりするリスクが生じるでしょう。含み益の大きい物件を移転する際は注意が必要です。
専門家への相談の重要性
不動産の法人活用は、税務や法務に関する専門的な知識が欠かせません。個人の資産状況、所有物件の特性、将来のライフプランなどによって最適なスキームは大きく違います。自己判断で進めると、かえって税負担が増えたり、思いもよらないトラブルにつながったりする可能性があります。そのため、不動産税務に詳しい税理士や司法書士といった専門家に相談することが重要です。
まとめ
不動産経営における法人活用は、所得税と法人税の税率差を利用した効果的な節税対策です。課税所得が一定額を超えたオーナーにとって、経費計上範囲の拡大や役員報酬による所得分散、さらには相続税対策など、メリットはいくつもあります。一方で、設立・維持コストや不動産移転時の税負担といった注意点も存在します。法人化という対策を成功させるカギは、自身の事業規模や将来設計に合わせた適切なタイミングの見極めと、緻密な計画です。不動産税務に精通した税理士などの専門家と連携し、個々の状況に最適な法人活用の形を模索することが、長期的な資産形成と安定した不動産経営の実現につながります。



コメント