相続財産に不動産が含まれる場合、その分割方法で悩むケースは少なくありません。不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人間で意見が対立し、トラブルに発展する可能性があります。
この記事では、相続した不動産を円満に分割するための基礎知識を解説します。この記事を読むことで、ご自身の状況に合った分割方法を理解し、スムーズな遺産分割を進めるための知識を得られるでしょう。
不動産相続における遺産分割の課題
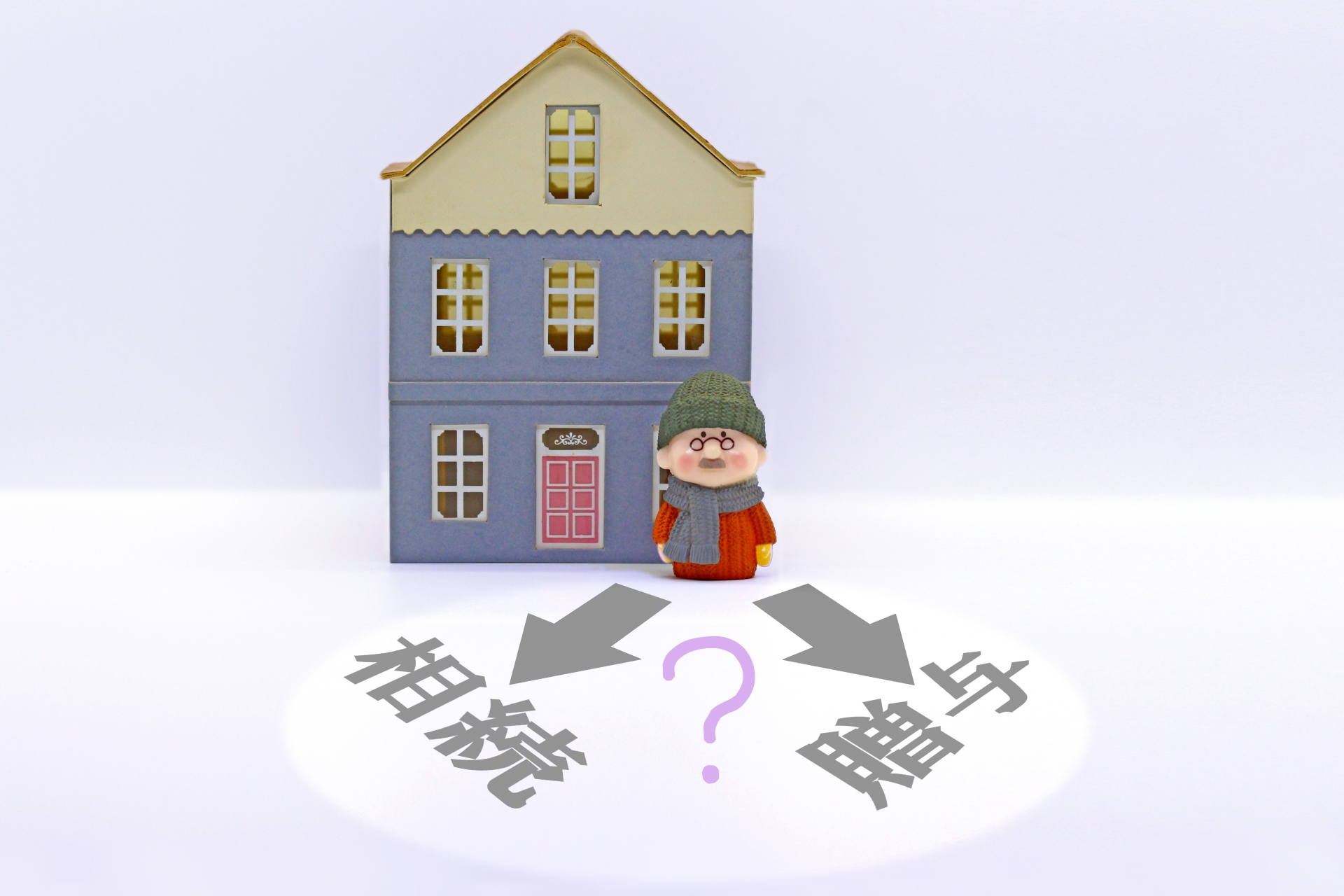
遺産分割とは、亡くなった方の財産を、相続する権利のある人の間で具体的に分配する手続きを指します。特に不動産は、遺産分割を進める上で多くの課題があり、トラブルの原因となりやすい財産です。
なぜ不動産の分割は揉めやすいのか?
不動産の分割が揉めやすい主な理由は、以下のとおりです。
- 動産は現金のように物理的に細かく分割できず、1円単位での公平な分け方が困難
- 不動産の評価基準が複数存在し、基準の選び方で対立が生じやすい
- 実家など特定の不動産に対する相続人の感情が分割協議を難しくする
- 分割方法によって相続人間で実質的な価値に差が出ることがあり、不公平感を生みやすい
- 共有名義による一時的な解決は、将来的な管理や売却時に新たなトラブルを招くリスクがある
不動産の分割は、物理的な制約や評価基準の違い、感情的対立、不公平感、将来リスクといった複合的な要素が絡むため、特に揉めやすい傾向にあります。
公平な遺産分割の基礎知識
遺産分割の基本的な考え方は、法律で定められた相続割合である「法定相続分」に応じて、相続人全員にとって公平になるように分けることです。しかし、不動産には以下のような特殊性があり、単純に法定相続分通りに分けることが難しい場合があります。
- 不動産は物理的に細かく分割しづらく、単純に法定相続分どおりに分けることが難しい
- 評価基準(時価、路線価、固定資産税評価額など)により価値が異なり、どの基準を採用するか全員の合意が必要
- 不動産の分割方法には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割があり、それぞれメリットとデメリットがある
- 代償分割では支払い能力や税負担、換価分割では売却コストや税金が課題となる
- 不動産の特殊性を踏まえ、公平性と実務面のバランスを考えた慎重な対応が求められる
不動産の遺産分割では、単なる法定相続分の適用にとどまらず、評価方法や分割手段、費用負担まで総合的に考慮し、公平性を実現することが不可欠です。
相続不動産の4つの分割方法とメリット・デメリット

相続した不動産を分割する方法は、主に以下の4つです。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。相続財産全体の状況や相続人それぞれの希望などを考慮して、最適な方法を選択することが重要です。どの方法を選択するかによって、手続きの手間、税金、将来的なリスクなどが異なります。
以下で、各分割方法について詳しく説明します。
現物分割
現物分割とは、相続財産である不動産そのものを、物理的に分割して各相続人が取得する方法です。例えば、広い土地を複数の区画に分けて登記し、それぞれの区画を相続人が取得する場合がこれに該当します。
現物分割のメリットとして、不動産を売却せ-pずにそのままの形で引き継ぐことができる点が挙げられます。また、売却に伴う仲介手数料や譲渡所得税などの費用が発生しません。分割後の価値が公平であれば、相続人間の不満が出にくい可能性もあります。
一方、デメリットとしては、土地の形状や日当たり、道路への接面状況などにより、分割後の土地の価値に差が出やすく、不公平感が生じる可能性があります。分筆によって土地が狭くなったり、使いにくい形になったりして、利用価値が低下することもあるでしょう。分割線上に建物がある場合は、建物の取り壊しが必要になるケースも考えられます。
換価分割
換価分割とは、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。物理的に分割しにくい不動産を、公平に分けることができるわかりやすい方法といえます。
換価分割のメリットは、売却代金を法定相続分などの明確な基準で分けられるため、公平性が高いことです。不動産を現金化できるため、相続税の納税資金や他の費用に充てることが可能です。管理が難しい遠方の不動産や、誰も利用する予定のない不動産を整理できます。
一方、デメリットとしては、思い出のある実家などを手放さなければならない点が挙げられます。また、希望する価格やタイミングで売却できるとは限りません。売却時には仲介手数料、登記費用、印紙税などの諸経費が発生します。売却によって利益が出た場合は、譲渡所得税や住民税が課税されます。市場状況によっては、想定より低い価格でしか売れない可能性もあるでしょう。
代償分割
代償分割とは、相続人の一人が不動産などの価値の高い遺産を現物で取得する代わりに、その相続人が他の相続人に対して、法定相続分などに見合う代償金を支払う方法です。
代償分割のメリットは、特定の相続人が不動産を取得できるため、そのまま住み続けたり、家業を継続したりすることが可能な点です。不動産を売却したり、無理に分割したりする必要がないため、資産価値を損なわずに済みます。代償金を支払うことで、不動産を取得しない他の相続人との間で公平性を保つことができるでしょう。
一方、デメリットとしては、不動産を取得する相続人に、代償金を支払うための十分な資力がなければ利用できない点が挙げられます。代償金の計算基礎となる不動産の評価額について、相続人間で意見が対立し、合意に至らない可能性があります。約束通りに代償金が支払われない場合、新たなトラブルの原因となるでしょう。
共有分割
共有分割とは、相続した不動産を特定の相続人が単独で取得したり、売却や分割をしたりせず、法定相続分などの割合に応じて、複数の相続人の共有名義にする方法です。
共有分割のメリットは、とりあえず法定相続分通りに分ける形になるため、一時的に遺産分割協議がまとまりやすいことがある点です。不動産を売却する必要がないため、単独所有にする場合に比べ、相続登記の手続き自体は比較的シンプルといえるでしょう。
一方、デメリットとしては、不動産の管理や修繕、賃貸借契約などを「管理行為」として行うには共有持分の過半数の同意が必要となる点です。不動産全体を売却したり、大規模な改修を「変更・処分行為」として行うには共有者全員の同意が必要となるため、意見がまとまらず意思決定が難しくなるケースが多い点が挙げられます。
不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要なため、一人でも反対者がいると売却できません。固定資産税や修繕費などの維持費の負担割合や支払い方法で揉める可能性があります。共有者の一人が亡くなると、その人の持分はさらにその相続人に引き継がれます。相続が繰り返されるたびに権利関係者が増え、関係性が希薄な人も含まれるようになり、最終的には合意形成が極めて困難になるでしょう。
分割できない不動産を相続する際の対処法

土地が狭小であったり、建物が建っていたりして物理的に分割が難しい、あるいは分割すると価値を大きく損ねてしまう不動産の場合、どのように分割すれば良いでしょうか。ここでは、そのような「分割できない不動産」への対処法を整理します。
対処法①「換価分割」を選ぶ場合は事前準備を徹底する
分割できない不動産を公平に分ける現実的な方法の一つが換価分割ですが、売却活動には時間がかかるため、相続税の申告期限に間に合わないリスクを想定しておきましょう。あらかじめ不動産会社に査定を依頼し、売却の目安時期や価格を確認しておくと安心です。
また、売却に伴い仲介手数料や登記費用、測量費用、解体費用などのコストが発生します。売却益が出た場合には譲渡所得税も考慮する必要があります。これらの費用負担や売却代金の分配方法について、相続人同士で事前に合意し、遺産分割協議書に明確に記載しておくことがトラブル防止のポイントです。
対処法②「代償分割」を選ぶ場合は支払い能力を事前に確認する
代償分割は、公平な分割手段として有効ですが、実行には十分な資金力が必要です。不動産の評価額によって代償金が高額になるケースも多く、支払い能力を超えてしまうリスクがあります。代償金の支払い方法を含め、事前に資金計画を立てましょう。
また、代償金の金額を決めるためには不動産の適正な評価が不可欠です。第三者による不動産鑑定を活用し、相続人間で評価額に納得した上で進めることが重要です。さらに、代償金の支払い条件を遺産分割協議書に明確に記載しないと、後日、贈与とみなされるリスクが生じるため、文書化を徹底しましょう。
対処法③「共有」は最終手段とし、出口戦略を設計しておく
分割できない不動産を相続人全員で共有する方法もありますが、原則として推奨されません。共有状態は「問題の先送り」に過ぎず、将来的なトラブルの温床となりやすいからです。
管理や修繕、売却などの判断に全員の合意が必要になるため、意思統一が難しく、物件の活用が進まないリスクがあります。どうしても共有を選ぶ場合は「将来、誰か一人が買い取る」「一定期間後に売却する」といった出口戦略を事前に設計しておくことが不可欠です。
対処法④賃貸活用で収益化するか、相続放棄を検討する
共有不動産を賃貸に出して、得た家賃収入を相続人間で分配する方法も選択肢の一つです。賃貸借契約には、共有持分の過半数の同意が必要です。ただし、賃貸経営には管理運営の手間、費用、空室リスクなどが伴います。家賃収入の分配ルールや、経費負担の方法もあらかじめ明確に決めておく必要があります。
また、不動産に関わりたくない場合や、負債が財産を上回る場合には、相続放棄を検討することも可能です。相続放棄は原則として、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。ただし、相続放棄をすると不動産以外の財産も一切受け取れなくなるため、慎重な判断が求められます。
不動産を遺産分割する具体的な流れ

不動産を含む遺産分割は、一般的に以下の流れで進められます。手続きには期限があるものもあるため、計画的に進めることが重要です。
ステップ1:遺言書の有無を確認する
最初に、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかを確認しましょう。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分割することになります。
確認場所としては、自宅の金庫や仏壇、貸金庫、懇意にしていた専門家、公証役場、法務局などが考えられます。遺言書は主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。検認は遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効性を判断するものではありません。封印された遺言書は、検認前に勝手に開封してはいけません。
ステップ2:相続人を調査・確定する
次に、誰が法的な相続人となるのかを正確に確定させる必要があります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を本籍地の市区町村役場から取り寄せます。これにより、配偶者の有無、子の有無などを全て確認しましょう。集めた戸籍謄本を基に、法定相続人を特定します。
確定した相続関係を図にまとめた「相続関係説明図」を作成すると、関係性がわかりやすくなり、後の手続きでも利用できるでしょう。相続人の現在の戸籍謄本や住民票も、遺産分割協議書作成や登記手続きで必要になります。
ステップ3:相続財産を調査・リスト化する
相続の対象となる財産を全て調査し、明確にします。
プラスの財産としては、不動産、預貯金、株式や投資信託、自動車、生命保険金、貴金属、骨董品などを調査します。マイナスの財産としては、借金、住宅ローン、未払いの税金や医療費、誰かの保証人になっていた場合の保証債務なども調査してください。
調査した全ての財産を一覧にした「財産目録」を作成します。プラスの財産とマイナスの財産を分けて記載し、評価額もわかる範囲で記入します。調査の結果、明らかにマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
ステップ4:不動産を評価する
相続財産の中に不動産が含まれる場合、遺産分割協議を進める上でその価値を評価しましょう。どの評価方法を遺産分割の基準とするか、相続人間で話し合い、合意します。先述したとおり、公平性の観点からは実勢価格に近い評価が望ましいと考えられます。
不動産会社に査定を依頼したり、固定資産評価証明書を取得したり、路線価図を確認したりして、評価額に関する資料を集めましょう。合意が難しい場合や客観的な評価が必要な場合は、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することも検討することが大切です。集めた評価に関する資料は、相続人全員で共有し、透明性を確保します。
ステップ5:遺産分割協議を行い、分割方法を決定する
確定した相続人全員が参加して、相続財産全体の分け方について話し合います。これが遺産分割協議です。遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。未成年者や認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、代理人を選任する必要があります。
作成した財産目録と不動産の評価額を基に、誰がどの財産をどれだけ取得するかを具体的に話し合いましょう。不動産については、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の中から、状況に合った方法を決定します。必ずしも法定相続分通りに分ける必要はなく、全員が合意すれば自由に分割割合を決めることができます。
ステップ6:遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で合意した内容は、後々のトラブル防止と、不動産の相続登記などの手続きのために「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
「誰が」「どの財産を」「どのように取得するか」を具体的に、かつ正確に記載しましょう。不動産の場合は、登記簿謄本の記載通りに、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などを正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書は、法的に有効な書類であり、後の手続きで重要な役割を果たします。内容に不備がないよう、専門家に作成を依頼するか、作成した内容のチェックを受けるのがおすすめです。
ステップ7:不動産の相続登記を行う
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書が作成されたら、不動産を取得した相続人へ名義を変更する手続きを、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記申請をしない場合、過料の対象となる可能性があります。
相続登記の手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたるため、司法書士に依頼するのが一般的です。相続登記を完了することで、不動産の権利関係が明確になり、将来的な売却や担保設定などがスムーズに行えるようになります。
不動産相続の分割でよくあるトラブルと回避策

不動産の遺産分割は、残念ながらトラブルに発展しやすいケースが多くあります。ここでは、よくあるトラブルのパターンとその回避策について解説します。
トラブル例1:分割方法で意見が対立する
相続人間で、不動産を「売りたい」「自分が住み続けたい」「先祖代々の土地だからそのまま残したい」など、希望する分割方法が異なり、意見が対立することがあります。各相続人の不動産に対する思い入れの違い、経済状況の違い、居住地の違いなどが背景にあることが多いです。
回避策としては、相続発生後、なるべく早い段階から相続人全員で話し合いの場を持ち、それぞれの意向や状況を確認し合うことが考えられます。不動産の評価額、各分割方法のメリットとデメリット、税金や費用の問題など、客観的な情報を全員で共有することも有効です。当事者同士では感情的になりやすい場合、弁護士などの専門家を間に入れて話し合いを進める方法もあります。また、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、分割方法を指定し、争いを未然に防ぐ効果が期待できます。
トラブル例2:不動産の評価額で揉める
遺産分割の基準となる不動産の評価額について、どの評価方法を用いるかで意見が対立することがあります。特に代償分割の場合、不動産を取得する側は低く、代償金を受け取る側は高く評価したいと考えがちです。評価方法によって金額が大きく異なることや、各相続人の利害が対立しやすいことが原因です。
回避策としては、まず、どの評価方法を用いるかについて、相続人全員で合意形成を図ることが挙げられます。公平性の観点から、実勢価格に近い評価を目指すのが望ましいと考えられます。
複数の不動産会社に査定を依頼する、または不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、客観的な評価額を基に協議することも有効です。税理士や弁護士に相談し、評価方法の選択や合意形成について助言を受けるようにしましょう。
トラブル例3:代償金の支払いができない・金額で揉める
代償分割を選択したいが、不動産を取得する相続人に代償金を支払う資力がない場合があります。あるいは、代償金の金額算定で揉めることもあります。合意した代償金が期日までに支払われず、新たな紛争に発展するケースもあるでしょう。不動産が高額であること、評価額の対立、取得希望者の資力不足、支払い計画の甘さなどが原因として考えられます。
回避策としては、代償分割を検討する際は、不動産を取得する相続人の支払い能力を事前に十分確認することが挙げられます。ローン利用なども含めて検討が必要です。先述したとおり、客観的な評価に基づき、評価額について合意することが重要です。
遺産分割協議書に、代償金の金額、支払方法、支払期日などを具体的に、かつ明確に記載する必要があります。分割払いの場合は、支払いが滞った場合に備えて、取得する不動産に抵当権を設定するなどの担保措置を検討することも有効です。
トラブル例4:共有名義にした後の管理・処分で対立する
とりあえず共有名義にしたものの、後日、不動産の修繕、賃貸、売却などを巡って共有者間で意見がまとまらないことがあります。固定資産税や管理費などの費用負担で揉めるケースもあります。共有不動産の意思決定には共有者の同意が必要であることや、時間が経つにつれて各共有者の状況や考え方が変化することが原因です。
回避策としては、共有分割は避け、他の分割方法を検討することが考えられます。共有は問題を先送りするだけの場合が多いからです。どうしても共有にする場合は、管理方法、費用負担、将来の処分方針などについて、事前に明確なルールを書面で定めておくことが重要です。共有者間で定期的に連絡を取り合い、不動産の状況や将来について話し合う機会を持つことも有効でしょう。
トラブル例5:遺留分を侵害してしまう
特定の相続人に不動産を集中して相続させる内容の遺言や遺産分割協議の結果、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、後から遺留分侵害額請求を受けることがあります。遺留分の制度を知らない、または軽視していることや、不動産の評価額を低く見積もりすぎていることが原因です。
回避策としては、遺言書を作成する際や、遺産分割協議を行う際には、各相続人の遺留分を考慮に入れることが挙げられます。遺留分の計算基礎となる財産を適正に評価することも重要です。遺留分に配慮した遺言書作成や遺産分割案について、弁護士や税理士に相談することも有効です。
不動産相続の分割で困ったときの相談先

不動産の遺産分割は、法律、税金、不動産評価など、さまざまな専門知識が必要となる場面が多くあります。自分たちだけで解決しようとせず、必要に応じて専門家のサポートを求めることが重要です。ここでは、主な相談先とその役割を紹介します。
税理士
税理士は、相続税額の計算と相続税申告書の作成、税務署への提出代行を行います。相続税の節税対策に関する助言も専門です。被相続人の準確定申告の代行、換価分割に伴う譲渡所得税の計算や申告に関する相談、納税資金に関する助言も行います。遺産総額が基礎控除額を超え、相続税申告が必要な場合や、節税対策を検討したい場合に相談すると良いでしょう。
弁護士
弁護士は、相続人間で意見が対立し、協議がまとまらない場合の交渉代理を行います。家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続き代理も主な役割です。遺留分侵害額請求など、法的な紛争が発生した場合の対応も行います。遺言書の有効性に関する争いや、遺言書作成のサポート、相続に関する全般的な法的助言、他の専門家との連携も担います。相続人間で争いが発生している、または発生しそうな場合や、法的な手続きが必要な場合に相談すると良いでしょう。
司法書士
司法書士は、不動産の相続登記手続きの専門家です。遺産分割協議書の作成サポートも行いますが、弁護士とは異なり、紛争性のある案件の交渉代理はできません。遺言書作成のサポート、相続放棄や限定承認の申述書作成サポート、法定相続情報証明制度の手続きサポートも行います。相続登記を行いたい場合や、相続人間で争いがなく、合意内容を遺産分割協議書にまとめたい場合に相談するのが適しています。
不動産鑑定士
不動産鑑定士は、不動産の客観的で専門的な評価額の算定を行います。鑑定評価書の作成も主な役割です。この評価書は、遺産分割協議、調停、審判、税務申告などで公的な証明力を持つ資料として利用できます。相続人間で不動産の評価額について争いがある場合や、公平な基準で評価額を決定したい場合、特殊な形状の土地や権利関係が複雑な不動産がある場合に相談するのが適しています。
不動産会社
不動産会社は、相続不動産の簡易査定や訪問査定を行います。換価分割を行う場合の不動産売却活動の仲介も担います。市場動向や売却戦略に関する助言、不動産を賃貸に出す場合の相談も可能です。換価分割を検討しており、不動産の売却相場を知りたい、または売却を依頼したい場合に相談すると良いでしょう。
まとめ
不動産の遺産分割は、その性質上、揉めやすい要素を多く含んでいます。しかし、適切な知識を持ち、手順を踏んで慎重に進めれば、円満な解決は十分に可能です。
相続が発生したら、早めに遺言書の確認、相続人調査、財産調査に着手することが重要です。4つの分割方法のメリットとデメリットを理解し、ご自身の状況に最も適した方法を相続人全員で検討する必要があります。安易な共有分割は将来のリスクを高める可能性がある点に注意が必要です。
公平な分割のためには、客観的な不動産評価が不可欠です。必要に応じて専門家の評価を利用しましょう。最も重要なのは、相続人全員が協力し、お互いの状況や気持ちを尊重しながら、冷静かつ丁寧に話し合い、合意形成を目指すことです。
トラブルを未然に防ぐためには、被相続人が生前に遺言書を作成したり、生命保険を活用したりするなどの対策が非常に有効です。手続きが複雑であったり、相続人間で話し合いがまとまらなかったりする場合は、決して一人で抱え込まず、専門家に早めに相談することが、円満解決への近道となります。



コメント